平屋でローコストなデザイナーズ住宅!マイホーム購入と住宅ローンや間取り
平屋で低価格、ローコストだけど、デザインや間取り、住宅の質にはこだわりたい! 設計士や建築家とともに建てるデザイナーズな一戸建て。
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ローコストなデザイナーズ住宅 ブラックの角波ガルバリウムの外壁工事を施工中です。
ローコストなデザイナーズ住宅 ブラックの角波ガルバリウムの外壁工事を施工中です。

いよいよ、外壁工事に入り、少しずつ外観の雰囲気がわかってきました。
我が家の外壁は日鐵住金鋼板株式会社 ニスクの耐磨カラーGLの耐磨ブラックです。
ブラックの外壁だと建物が引き締まってシャープに見えますし、金属の外壁だからこそ、表現できる黒色の締まった外壁でもありますね。
また、暗めの色は金属の重厚感を醸し出す効果もあるので、ガルバリウム鋼板という薄い金属板に合う色だと思いました。
近くで見ると、凹凸があり、金属外壁ならではのエッジの効いた角波がいい感じの雰囲気です。
ブラック系のガルバリウム鋼板は夏場は、遮熱塗装がされているとはいえ、素手でさわれないほど熱くなります。
ホワイト系も熱くなりますが、ブラック系ほどではありません。
特に、工事中しか触れませんが、ガルバリウム鋼板の裏側の金属の地金部分などは、本当に熱くなり、火傷に注意しないといけないほどです。
ガルバリウム鋼板は金属の薄い板なので軽くて作業性も良いようですね。
夏場の作業は大変みたいですが…
また、金属なので、エッジの部分や切断面は大変鋭利な状態ですから、施工中に見学するときには気をつけましょう!
いよいよ、外壁工事に入り、少しずつ外観の雰囲気がわかってきました。
我が家の外壁は日鐵住金鋼板株式会社 ニスクの耐磨カラーGLの耐磨ブラックです。
ブラックの外壁だと建物が引き締まってシャープに見えますし、金属の外壁だからこそ、表現できる黒色の締まった外壁でもありますね。
また、暗めの色は金属の重厚感を醸し出す効果もあるので、ガルバリウム鋼板という薄い金属板に合う色だと思いました。
近くで見ると、凹凸があり、金属外壁ならではのエッジの効いた角波がいい感じの雰囲気です。
ブラック系のガルバリウム鋼板は夏場は、遮熱塗装がされているとはいえ、素手でさわれないほど熱くなります。
ホワイト系も熱くなりますが、ブラック系ほどではありません。
特に、工事中しか触れませんが、ガルバリウム鋼板の裏側の金属の地金部分などは、本当に熱くなり、火傷に注意しないといけないほどです。
ガルバリウム鋼板は金属の薄い板なので軽くて作業性も良いようですね。
夏場の作業は大変みたいですが…
また、金属なので、エッジの部分や切断面は大変鋭利な状態ですから、施工中に見学するときには気をつけましょう!
PR
ローコストなデザイナーズ住宅 床材はパナソニックのベリティス フローリングに決定!
ローコストなデザイナーズ住宅 床材はパナソニックのベリティス フローリングに決定!

フローリングの床材はパナソニックのベリティスにしました。
ベリティスは昨年、パナソニックの新しい建材ブランドとしてリニューアルしています。
扉やフローリングも色が増え、プリントされるデザインも最近の流行を取り入れた本物の木みたいな柄の違いを楽しめるものや、幅広のタイプなどがラインナップに加わりました。
ベリティスを選んだ1番の理由は、お手頃な価格で、他の一般的なフローリングに比べて、単調じゃない変化にとんだ柄のデザインや幅広のタイプなどが決めてでした。
パナソニックが住宅事業に力を入れている中で、リニューアルした製品なだけに、コストパフォーマンスは高い製品だと思います。
ベリティスのフローリングには、本物の突き板を利用したものやより質感にこだわったもの、特殊な着色塗装を採用したものなど、色々な種類がありますが、採用したのは一番標準的なシートタイプでベリティス フィットフロアーです。
価格は定価で坪10000円で、色はほぼブラック色である、スモークオーク柄です。
今回のフローリングを決めるまでには、色々なサンプルを取り寄せ、ショールームを見て、比較をしました。
無垢材は、強い憧れがありましたが、本物のオークやウォルナットなどのダーク系の樹種は値段が高かったり、ワックスなどの手入れが大変で、本物の木なので簡単に傷がつきやすく、表明が柔らかいため扱いが難しいことがわかりました。
実際に取り寄せた無垢材のカットサンプルで、わざと傷をつけたり、汚してみたりして感じたことは、しっかりと手入れができたり、変化を楽しむ余裕がある人でないと難しいなぁと思いました。
無垢材に近い品質の厚めの突き板タイプや本物の突き板なども検討しましたが、値段が高めなことや、無垢材ほどではないですが、傷がつきやすいこと、表面は本物の木なので、フローリングや見た目やデザインなどが逆に単調になりやすく、値段以上のメリットが感じられませんでした。
実は、今回選んだシートタイプも、実際は木質合板に木柄をプリントしたシートを貼り付けてあるだけなので、深い傷やシートが破れるような傷は修復がしにくいという大きなデメリットがあります。
と言っても、他のフローリングに比べてかなり傷はつきにくく、そこまで大きく目だつものでなければいい、と割り切った部分もあります。
フローリングは毎日触れて、目に入るものなので、質感や見た目にこだわるべきだと思います。
ベリティスで本当にいいのかな?とかなり悩みましたが、パナソニックのショールームや建材やフローリングの展示会で実際に見て、ベリティスのデザインと価格を他のものと比較しても、製品のコストパフォーマンスは高いと思いました。
実際に床が貼られたら改めて確認したいと思います。
フローリングの床材はパナソニックのベリティスにしました。
ベリティスは昨年、パナソニックの新しい建材ブランドとしてリニューアルしています。
扉やフローリングも色が増え、プリントされるデザインも最近の流行を取り入れた本物の木みたいな柄の違いを楽しめるものや、幅広のタイプなどがラインナップに加わりました。
ベリティスを選んだ1番の理由は、お手頃な価格で、他の一般的なフローリングに比べて、単調じゃない変化にとんだ柄のデザインや幅広のタイプなどが決めてでした。
パナソニックが住宅事業に力を入れている中で、リニューアルした製品なだけに、コストパフォーマンスは高い製品だと思います。
ベリティスのフローリングには、本物の突き板を利用したものやより質感にこだわったもの、特殊な着色塗装を採用したものなど、色々な種類がありますが、採用したのは一番標準的なシートタイプでベリティス フィットフロアーです。
価格は定価で坪10000円で、色はほぼブラック色である、スモークオーク柄です。
今回のフローリングを決めるまでには、色々なサンプルを取り寄せ、ショールームを見て、比較をしました。
無垢材は、強い憧れがありましたが、本物のオークやウォルナットなどのダーク系の樹種は値段が高かったり、ワックスなどの手入れが大変で、本物の木なので簡単に傷がつきやすく、表明が柔らかいため扱いが難しいことがわかりました。
実際に取り寄せた無垢材のカットサンプルで、わざと傷をつけたり、汚してみたりして感じたことは、しっかりと手入れができたり、変化を楽しむ余裕がある人でないと難しいなぁと思いました。
無垢材に近い品質の厚めの突き板タイプや本物の突き板なども検討しましたが、値段が高めなことや、無垢材ほどではないですが、傷がつきやすいこと、表面は本物の木なので、フローリングや見た目やデザインなどが逆に単調になりやすく、値段以上のメリットが感じられませんでした。
実は、今回選んだシートタイプも、実際は木質合板に木柄をプリントしたシートを貼り付けてあるだけなので、深い傷やシートが破れるような傷は修復がしにくいという大きなデメリットがあります。
と言っても、他のフローリングに比べてかなり傷はつきにくく、そこまで大きく目だつものでなければいい、と割り切った部分もあります。
フローリングは毎日触れて、目に入るものなので、質感や見た目にこだわるべきだと思います。
ベリティスで本当にいいのかな?とかなり悩みましたが、パナソニックのショールームや建材やフローリングの展示会で実際に見て、ベリティスのデザインと価格を他のものと比較しても、製品のコストパフォーマンスは高いと思いました。
実際に床が貼られたら改めて確認したいと思います。
ローコストなデザイナーズ住宅 設計士はどうやって探す?
ローコストなデザイナーズ住宅 設計士を選ぶポイント
ローコストなデザイナーズ住宅を建てるには自分たちにあった設計士の選択がとても重要になってきます。
そこで、設計士を選ぶ際のポイントについてまとめてみました。
最近では、ネットやネットワークなどで、設計士を選ぶためのコンペをすることもあるようですが、一度きりのコンペだけでは、本当の良さはわからないと思います。
なぜなら、最初に希望した基本的なプランから、現実の建築までに内容をかなり変更して行くからです。
最初の提案では、こちらが伝えた要望から現実的な設計や理想の住宅を設計できそうか?のフィーリングが合うかどうかを確かめるという認識でお願いするといいと思います。
特に、設計士が、今まで手がけた設計の建築内容や過去に設計した実績を確認させてもらうと、どんな建物が得意か、予算規模は適正かどうかが見えてくると思います。
また、設計士は設計するだけでなく、マイホームの建築という大変時間がかかる作業を一緒に進めていくパートナーとして、対応やサービスはどうか?をしっかり確認しておきたいですね。
特に建築には現場でのトラブルや決定までの細かい悩みがつきものなので、どんなことも相談に乗ってくれるか、こちらの要望や課題に対して、積極的な提案があるかどうか、あくまで主役は施主であるという姿勢か、を重視するといいと思います。
また、設計士にお願いするのに、忘れがちなのが、設計料金や予算管理です。
設計士が提案する設計金額は適正かどうかだけでなく、こちらの土地購入や建築費に対する総予算内で、設計料金も含めて完成までの予算管理ができるかどうか、予算内で実現するために具体的な提案があるかどうかを確認しておきたいですね。
また、設計料金が安い、高いは同じ金額でも仕事の内容でかなり変わります。
例えば、ただ設計して終わりなのか、は一番当たり前の事ですか、設計士は建築のコンサルタントとして、全体の総予算管理はしっかりやってくれるのか、細かい提案や相談にも親身に応じてくれるかは、重視したいポイントですね。
基本設計や実施設計の内容や作成だけでなく、その後の現場での細かい変更でも快く対応してくれるのか、設計後の現場管理も工務店や大工などの現場監督任せではなく、しっかりと見てくれ、報告もしてくれるのか?という点は施主の負担を減らすだけに必ず確認しておくといいと思います。
ローコストなデザイナーズ住宅を建てるには自分たちにあった設計士の選択がとても重要になってきます。
そこで、設計士を選ぶ際のポイントについてまとめてみました。
最近では、ネットやネットワークなどで、設計士を選ぶためのコンペをすることもあるようですが、一度きりのコンペだけでは、本当の良さはわからないと思います。
なぜなら、最初に希望した基本的なプランから、現実の建築までに内容をかなり変更して行くからです。
最初の提案では、こちらが伝えた要望から現実的な設計や理想の住宅を設計できそうか?のフィーリングが合うかどうかを確かめるという認識でお願いするといいと思います。
特に、設計士が、今まで手がけた設計の建築内容や過去に設計した実績を確認させてもらうと、どんな建物が得意か、予算規模は適正かどうかが見えてくると思います。
また、設計士は設計するだけでなく、マイホームの建築という大変時間がかかる作業を一緒に進めていくパートナーとして、対応やサービスはどうか?をしっかり確認しておきたいですね。
特に建築には現場でのトラブルや決定までの細かい悩みがつきものなので、どんなことも相談に乗ってくれるか、こちらの要望や課題に対して、積極的な提案があるかどうか、あくまで主役は施主であるという姿勢か、を重視するといいと思います。
また、設計士にお願いするのに、忘れがちなのが、設計料金や予算管理です。
設計士が提案する設計金額は適正かどうかだけでなく、こちらの土地購入や建築費に対する総予算内で、設計料金も含めて完成までの予算管理ができるかどうか、予算内で実現するために具体的な提案があるかどうかを確認しておきたいですね。
また、設計料金が安い、高いは同じ金額でも仕事の内容でかなり変わります。
例えば、ただ設計して終わりなのか、は一番当たり前の事ですか、設計士は建築のコンサルタントとして、全体の総予算管理はしっかりやってくれるのか、細かい提案や相談にも親身に応じてくれるかは、重視したいポイントですね。
基本設計や実施設計の内容や作成だけでなく、その後の現場での細かい変更でも快く対応してくれるのか、設計後の現場管理も工務店や大工などの現場監督任せではなく、しっかりと見てくれ、報告もしてくれるのか?という点は施主の負担を減らすだけに必ず確認しておくといいと思います。
吹き付け断熱の施工方法と断熱性
吹き付け断熱の施工方法と断熱性

我が家の断熱工事も無事に終了しましたので、今回わかった吹き付け断熱の施工方法と注意点などを報告したいと思います。
吹き付け断熱は、日本アクアのアクアフォームや、アイシネンフォームなどの商品が有名です。
二つの液体を混ぜ合わせ、壁などに吹き付けるとウレタンフォームに膨らんでそのまま固まります。
最初は液体で膨らんでいくので、細かい隙間や複雑な形状の部分にも泡が膨らんで行くのでしっかりと埋めることができます。
特に金物や、電源、スイッチの配線部分、チューブや配管の外周部など、断熱処理がやりづらいところもしっかりと泡が膨らんで隙間を塞いでくれます。
施工方法ですが、吹き付け工事のタイミングは、電気配線や通気口、排気口、パイプなどをあらかじめ施工してから吹き付けとなります。
吹き付け断熱の注意点としては、電源コンセントの位置やスイッチの位置、照明の取り付け位置は、構造やサッシの取り付けが出来上がるころなど、早めの段階で決めておく必要があります。
また、確認を忘れがちなテレビ配線やLAN配線、給湯器のモニター、インターホン、エアコンの設置位置なども電気工事の担当者と早めに確認しておきましょう。
さらに、吹き付けると柱はほとんど見えなくなりますので写真などでどこに柱があるかを把握できるように記録しておきましょう。
そして、天井には外壁の内側の壁と断熱剤の隙間をつくり、通気スペーサーとなる通気用のダンボールを貼り付けます。
そこまでが、現場大工や電気工事の担当となります。
その後はウレタン吹き付け断熱の施工会社の担当となります。
液体のウレタンフォームと吹き付けポンプを積んだトラックがやって来て、作業員2人の方がテキパキとこなします。
施工時は締め切りで、上下カッパのような作業服やマスク、帽子などの格好になりますので、夏場などはかなりの重労働になります。
吹き付けの前に、まず吹き付ける必要のない、梁や電源部分、サッシ、床面などを丁寧に養生します。
そして、準備が終わったら一気に吹き付けて行きます。
しかし、吹き付けも決められた一定の厚みになるように丁寧に、均一に、外の伝熱になりやすい金物やボルトなどもしっかりと吹き付けて行きます。
一通り断熱剤の吹き付けが終わると、厚めに吹き付けた部分を設計で決められた平らの厚さになるように削ぎ落として行きます。
素人的にはせっかく厚く吹いたならそのままの方が、と思うのですが、正しい厚さにしておかないと、その後の工事の支障になってしまいますね。
ちなみに、そぎ落とした断熱剤はかなりの量になります。
吹き付けたウレタンフォームは、弾力は強く結構強く押さないと凹みませんし、凹んでも元に戻ります。
そぎ落とした断熱材や養生を剥がして元に戻すと断熱工事の終了です。

断熱工事後の室内はなんとなく、気持ちの問題かもしれないですが外気と違う気がします。
実際には、住んでみて真夏の暑さや真冬の寒さをどれくらい断熱できるかだと思いますが、その辺はまた住んでみてレポートしてみたいと思います。
我が家の断熱工事も無事に終了しましたので、今回わかった吹き付け断熱の施工方法と注意点などを報告したいと思います。
吹き付け断熱は、日本アクアのアクアフォームや、アイシネンフォームなどの商品が有名です。
二つの液体を混ぜ合わせ、壁などに吹き付けるとウレタンフォームに膨らんでそのまま固まります。
最初は液体で膨らんでいくので、細かい隙間や複雑な形状の部分にも泡が膨らんで行くのでしっかりと埋めることができます。
特に金物や、電源、スイッチの配線部分、チューブや配管の外周部など、断熱処理がやりづらいところもしっかりと泡が膨らんで隙間を塞いでくれます。
施工方法ですが、吹き付け工事のタイミングは、電気配線や通気口、排気口、パイプなどをあらかじめ施工してから吹き付けとなります。
吹き付け断熱の注意点としては、電源コンセントの位置やスイッチの位置、照明の取り付け位置は、構造やサッシの取り付けが出来上がるころなど、早めの段階で決めておく必要があります。
また、確認を忘れがちなテレビ配線やLAN配線、給湯器のモニター、インターホン、エアコンの設置位置なども電気工事の担当者と早めに確認しておきましょう。
さらに、吹き付けると柱はほとんど見えなくなりますので写真などでどこに柱があるかを把握できるように記録しておきましょう。
そして、天井には外壁の内側の壁と断熱剤の隙間をつくり、通気スペーサーとなる通気用のダンボールを貼り付けます。
そこまでが、現場大工や電気工事の担当となります。
その後はウレタン吹き付け断熱の施工会社の担当となります。
液体のウレタンフォームと吹き付けポンプを積んだトラックがやって来て、作業員2人の方がテキパキとこなします。
施工時は締め切りで、上下カッパのような作業服やマスク、帽子などの格好になりますので、夏場などはかなりの重労働になります。
吹き付けの前に、まず吹き付ける必要のない、梁や電源部分、サッシ、床面などを丁寧に養生します。
そして、準備が終わったら一気に吹き付けて行きます。
しかし、吹き付けも決められた一定の厚みになるように丁寧に、均一に、外の伝熱になりやすい金物やボルトなどもしっかりと吹き付けて行きます。
一通り断熱剤の吹き付けが終わると、厚めに吹き付けた部分を設計で決められた平らの厚さになるように削ぎ落として行きます。
素人的にはせっかく厚く吹いたならそのままの方が、と思うのですが、正しい厚さにしておかないと、その後の工事の支障になってしまいますね。
ちなみに、そぎ落とした断熱剤はかなりの量になります。
吹き付けたウレタンフォームは、弾力は強く結構強く押さないと凹みませんし、凹んでも元に戻ります。
そぎ落とした断熱材や養生を剥がして元に戻すと断熱工事の終了です。
断熱工事後の室内はなんとなく、気持ちの問題かもしれないですが外気と違う気がします。
実際には、住んでみて真夏の暑さや真冬の寒さをどれくらい断熱できるかだと思いますが、その辺はまた住んでみてレポートしてみたいと思います。
ほぼ平屋のデザイナーズローコスト住宅 サッシ窓枠がつきました!
ほぼ平屋のデザイナーズローコスト住宅 サッシ窓枠がつきました!

我が家のサッシはリクシルのもっともスタンダードなサッシであるデュオPGにしました!
サッシ自体は金属のアルミサッシですが、一部がプラスチックで覆われていて結露がおきにくくなっています。
リクシルのショールームでは、デュオPGはスタンダードな窓として、サーモスⅡなどと比較すると非常に安っぽいですが、実際に取り付けられるとこれで十分って感じですね。
窓自体はシングルガラスとペアガラスがあり、ペアガラスには、ロウイーと言われる断熱フィルムが貼られた断熱タイプや遮熱タイプがあります。
うちのデュオPGはただのペアガラスでしたが、ガラス屋さんのサービスで、料金そのままで、南面の窓を遮熱タイプに変更することができました!
ロウイーの窓ガラスには、フィルムをペアガラスのどちらの窓に貼るかで、遮熱タイプと断熱タイプにわかれます。
遮熱タイプの方が、断熱タイプに比べて紫外線カット率が高く、断熱性も高い特徴があり、我が家では、遮熱タイプにしました。
色は遮熱タイプがほんのりグリーンで断熱タイプがシルバーです。
色は外から見てもあまりわかりませんが、室内から見た方がほんのりグリーンがかっているのがわかる感じですね。

ペアガラスだと、ガラスが二枚なので重いイメージがありますが、動きはスムーズです。
今回はサッシと一緒にドアもつきました。
玄関ドアは同じくリクシルのデザイナーズドアです。
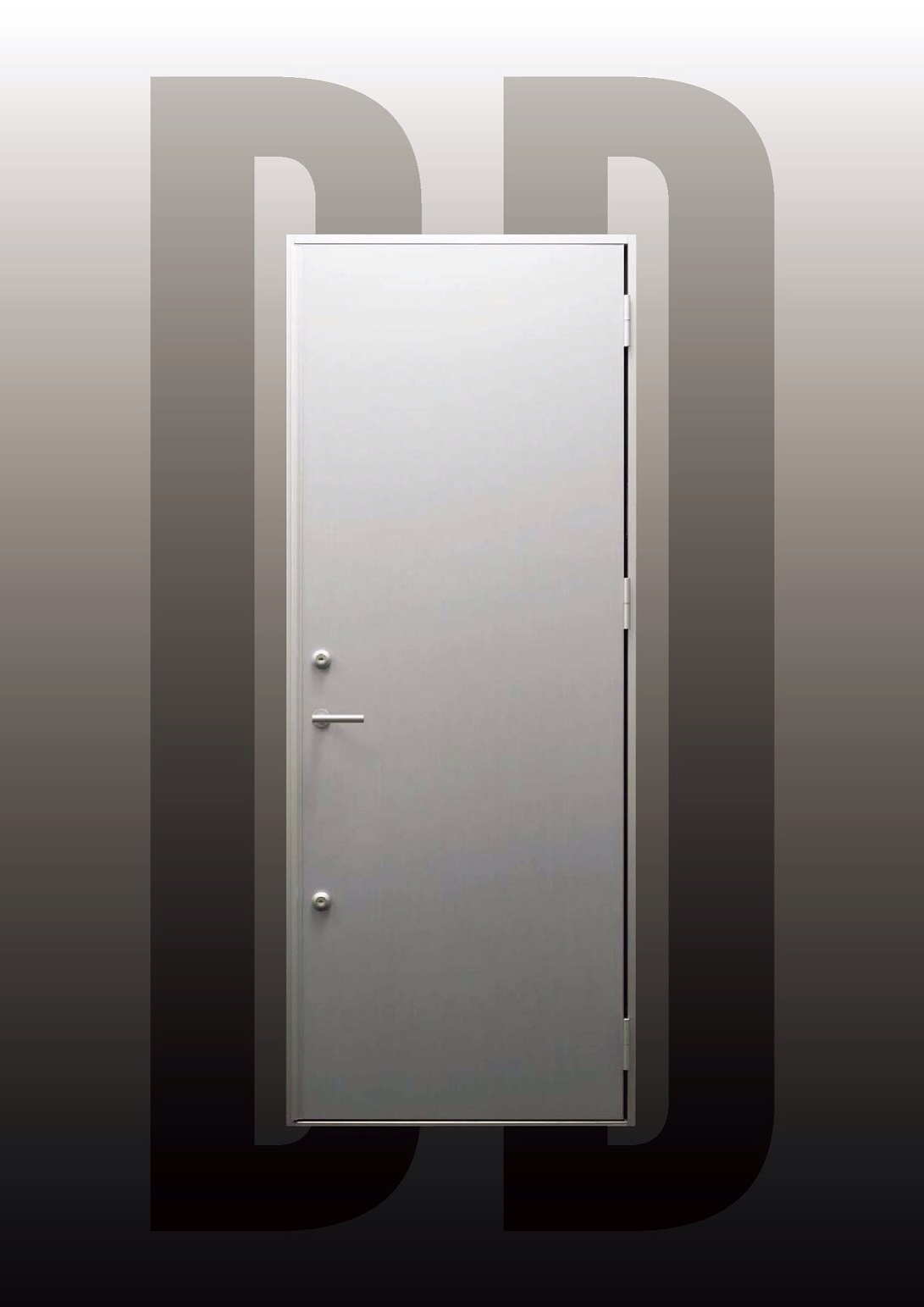
他にもドアがついているのですが、足場と干渉するので勝手口のドアやテラスドアはまだ開けることができません。
網戸もまだ着いていないのですが、窓やドアが着いて外観はかなり家らしくなってきました!
我が家のサッシはリクシルのもっともスタンダードなサッシであるデュオPGにしました!
サッシ自体は金属のアルミサッシですが、一部がプラスチックで覆われていて結露がおきにくくなっています。
リクシルのショールームでは、デュオPGはスタンダードな窓として、サーモスⅡなどと比較すると非常に安っぽいですが、実際に取り付けられるとこれで十分って感じですね。
窓自体はシングルガラスとペアガラスがあり、ペアガラスには、ロウイーと言われる断熱フィルムが貼られた断熱タイプや遮熱タイプがあります。
うちのデュオPGはただのペアガラスでしたが、ガラス屋さんのサービスで、料金そのままで、南面の窓を遮熱タイプに変更することができました!
ロウイーの窓ガラスには、フィルムをペアガラスのどちらの窓に貼るかで、遮熱タイプと断熱タイプにわかれます。
遮熱タイプの方が、断熱タイプに比べて紫外線カット率が高く、断熱性も高い特徴があり、我が家では、遮熱タイプにしました。
色は遮熱タイプがほんのりグリーンで断熱タイプがシルバーです。
色は外から見てもあまりわかりませんが、室内から見た方がほんのりグリーンがかっているのがわかる感じですね。
ペアガラスだと、ガラスが二枚なので重いイメージがありますが、動きはスムーズです。
今回はサッシと一緒にドアもつきました。
玄関ドアは同じくリクシルのデザイナーズドアです。
他にもドアがついているのですが、足場と干渉するので勝手口のドアやテラスドアはまだ開けることができません。
網戸もまだ着いていないのですが、窓やドアが着いて外観はかなり家らしくなってきました!
おすすめ情報

カスタム検索
最新記事
(04/06)
(03/16)
(01/21)
(01/20)
(01/18)
プロフィール
HN:
安く低価格だけどデザインや間取り、住宅の質にはこだわる施主
性別:
非公開
自己紹介:
現在はアパート暮らし、だけどやっと念願のマイホームを手に入れます。
新築や、家について気になったことを書きたいと思います。
不動産や土地探しから、住宅ローンや住宅ローン控除、最近のデザイナー住宅、気になる間取り、家の構造や建築材料、住宅設備などの情報もご紹介します。。
新築や、家について気になったことを書きたいと思います。
不動産や土地探しから、住宅ローンや住宅ローン控除、最近のデザイナー住宅、気になる間取り、家の構造や建築材料、住宅設備などの情報もご紹介します。。
ブログ内検索
カテゴリー
